行政書士試験の学習、お疲れ様です。
これまで、国会・内閣・裁判所と、日本の統治機構を個別に学んできました。今回はその総仕上げとして、3つの機関が互いにどう影響し合っているのか、その全体像を「三権分立」という視点から解き明かします。
- 国会から内閣へのチェック機能、3つ以上言えますか?
- 内閣から国会へのチェック機能は?
- 裁判所は、他の二権をどう見張っている?
これまで学んだ断片的な知識が、この記事で一本の線として繋がります。統治機構を得点源にするための最後のピース、一緒に埋めていきましょう。
【統治総まとめ】三権分立と抑制・均衡
権力分立の理論と実際【行政書士試験対策】
1. 三権分立の目的と本質
統治機構の学習、お疲れ様です。今回はその総まとめとして、国会・内閣・裁判所の関係性を「三権分立」という視点から見ていきましょう。
三権分立とは、国家権力を立法・行政・司法の三つに分け、異なる機関に担当させることで、権力の集中と濫用を防ぎ、国民の権利と自由を守ることを目的とした憲法の基本原理です。
二つの側面で理解する
- 権力分立:権力を性質で分け、別の機関に担当させること。
- 抑制と均衡 (チェック・アンド・バランス):各機関が互いに監視・牽制し合い、バランスを保つこと。
2. 【最重要】抑制と均衡の具体的メカニズム
各機関が互いにどのようなチェック機能を持っているのか、以下の関係表で全体像を掴みましょう。これまで学んだ知識が、この表の中で有機的に繋がります。
国会(立法)
内閣不信任決議
国政調査権
予算の議決
弾劾裁判所の設置
裁判官の報酬決定
内閣(行政)
衆議院の解散
法案提出
予算案提出
最高裁長官の指名
裁判官の任命
裁判所(司法)
違憲審査権(法律)
法律の無効宣言
違憲審査権(命令・処分)
行政処分の取消
抑制・均衡のポイント
国会 ⇄ 内閣
議院内閣制により密接な関係。国会が内閣を統制し、内閣が国会を牽制。
司法の独立
裁判所は他の機関から独立し、違憲審査権により憲法の番人として機能。
相互監視
各機関が互いを監視することで、権力の濫用を防ぐシステムを構築。
3. 日本の三権分立の特徴と試験での問われ方
日本の三権分立は、厳格な分離を採るアメリカ大統領制とは異なり、特に国会と内閣が密接に連携する「議院内閣制」を基軸としている点が最大の特徴です。
行政書士試験では、この関係性を踏まえ、以下のような知識が問われます。
- 制度の正確な理解:内閣不信任決議の主体(衆議院のみ)、法律案の再可決要件(出席議員の3分の2)など、各制度の詳細。
- 権能の帰属:「条約の締結は内閣、承認は国会」のように、具体的な権能がどの機関に属するかの正確な振り分け。
- 理念の理解:「国権の最高機関=政治的美称」など、各機関の地位を示す言葉の憲法上の意味。
個別の知識だけでなく、「なぜその制度があるのか?」という抑制・均衡の視点を持つことが、応用力を高める上で非常に重要です。

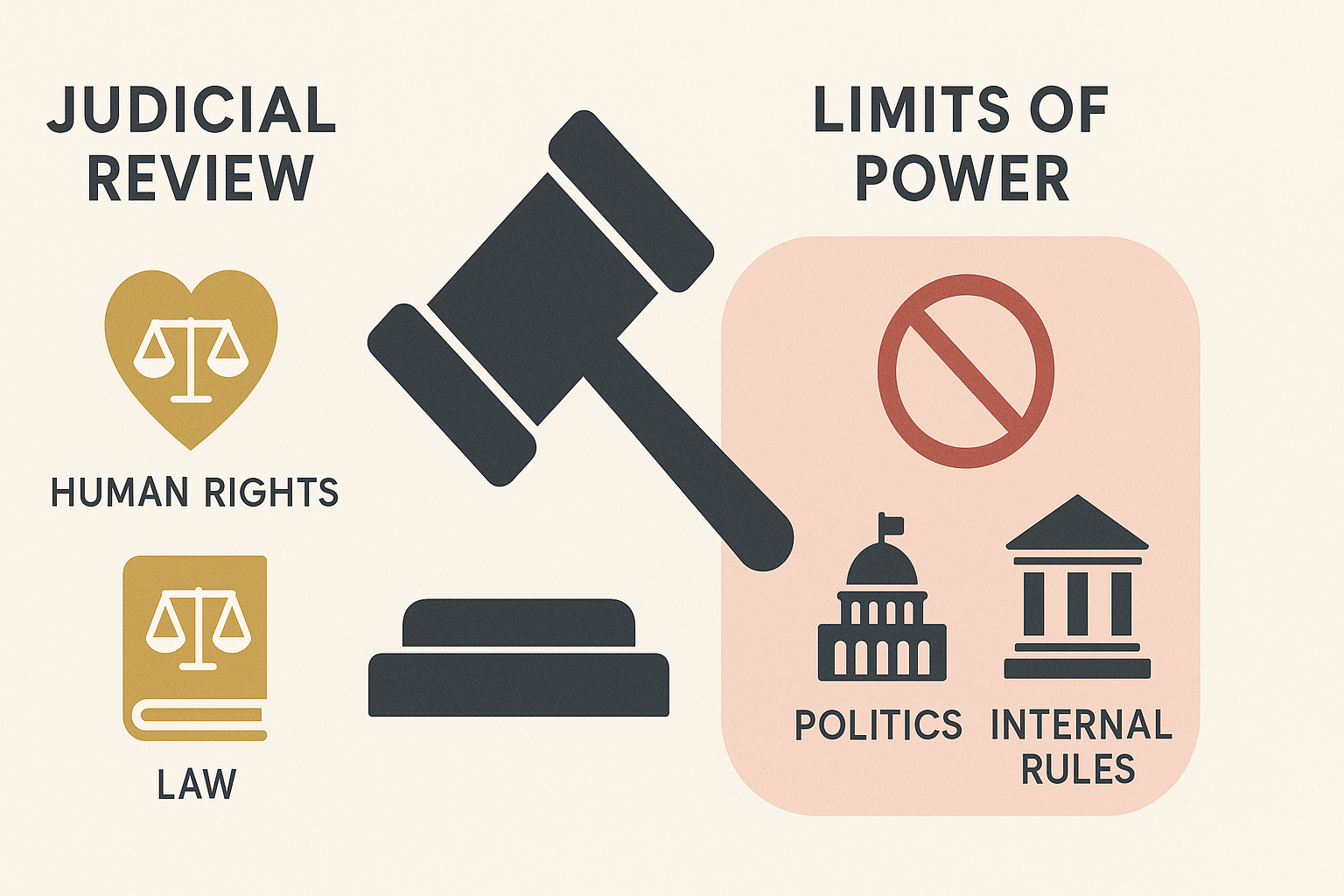

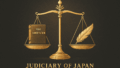

コメント