行政書士試験の学習、お疲れ様です。
今回は、人権分野の中でも特に繊細で、判例の深い理解が求められる「信教の自由」を取り上げます。
- 信教の自由に含まれる「3つの自由」を、制約の有無と共に説明できますか?
- 政教分離の判断基準「目的・効果基準」とは、具体的にどんな内容ですか?
- なぜ、津地鎮祭はOKで、愛媛の玉ぐし料はNGだったのでしょうか?
これらの問いに明確に答えられないなら、この記事はあなたのためのものです。複雑に見える判例理論も、ポイントを絞って図解で整理すれば、必ず得意分野に変わります。精神的自由権の核心を、一緒に攻略していきましょう。
信教の自由と政教分離
内心の自由と国家の中立性【行政書士試験対策】
1. 信教の自由の三つの柱 (憲法20条)
精神的自由権の核心である「信教の自由」。何を信じ、何を心の拠り所とするかは、個人の人格形成の根幹をなす最も繊細な領域です。憲法20条1項が保障する自由は、三つの要素に分解して理解するのがポイントです。
-
① 信仰の自由(内心の自由) 特定の宗教を信じる・信じない自由。国家権力による制約が一切許されない絶対的自由です。
-
② 宗教的行為の自由 礼拝、布教、儀式などを行う自由。外部的行為であるため、公共の福祉による制約を受けます。
-
③ 宗教的結社の自由 宗教団体を設立・運営・参加する自由。これも外部的行為なので、公共の福祉による制約を受けます。
2. 政教分離の原則となぜ「例外」があるのか?
信教の自由を実質的に保障するための大原則が「政教分離」です。国家と宗教が結びつくことで、過去に国民の自由が侵害された歴史への深い反省に基づいています。
しかし、国家と宗教の関わりを一切禁じると、現実社会に支障が出ます。そこで判例は、その関わりが許されるかどうかの判断基準を示しました。これが最重要判例・津地鎮祭事件で確立された「目的・効果基準」です。
ある行為が憲法の禁じる「宗教的活動」にあたるかは、以下の基準で判断されます。
- 行為の目的が、宗教的意義を持つか?
- その効果が、宗教への援助、助長、促進または圧迫、干渉になるか?
※これらを、社会通念に照らして客観的に判断する。
3. 【判例比較】同じ基準でなぜ結論が違う?
「目的・効果基準」を適用した二つの代表的な判例を比較することで、理解を深めましょう。同じ基準を使っても、事案によって結論が分かれる点が試験で狙われます。
津地鎮祭事件
市立体育館の建設に際し、市が神式の地鎮祭を主催し、公金を支出した事案。
理由:目的は工事の安全祈願という世俗的なもの。効果も神道を特別に援助するものではない。
愛媛玉ぐし料訴訟
愛媛県が、靖国神社等へ玉ぐし料などを公金から支出した事案。
理由:目的も効果も特定の宗教団体との関わりを相当限度を超えて持ったものと評価された。
本日のまとめ
信教の自由は、絶対的な「内心の自由」と、制約を受ける「外部的行為の自由」から構成されます。そして、この自由を支える政教分離の原則は、「目的・効果基準」という判例法理によって、柔軟に解釈・運用されていることを理解することが、この分野の得点力を高める鍵となります。


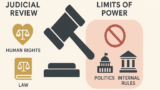
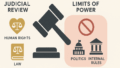
コメント