「本当の平等」ってなんだろう?
憲法14条から学ぶ、違いを力に変える考え方
すべての始まり、憲法14条の約束
「みんな平等に」「それって不公平じゃない?」——私たちは、仕事や暮らしの中で、ごく自然に「平等」という言葉を使います。しかし、その意味は意外と奥深いものです。
まず、私たちの国の最高法規である「日本国憲法」が、このテーマについてどう語っているかを見てみましょう。
第14条第1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
これは、「生まれや性別など、自分の努力で変えられないことで、誰も不当に扱われることはない」という、国からの力強い約束なのです。
「全員、同じ扱い」が招くワナ
「法の下に平等」と聞くと、「全員をまったく同じに扱えばいい!」と思いがちです。これを形式的平等と言います。しかし、本当にそれで良いのでしょうか?有名な例え話で考えてみましょう。

もし、背の高さが違う3人に同じ高さの台を配ったら…?
背が高い人は余裕で見えますが、車椅子の人には踏み台が役に立たず、ショーを楽しむことができません。同じものを与えたのに、結果として「見える人」と「見えない人」という不平等が生まれてしまいました。
目指すべきは、車椅子の人にスロープを用意するような、結果としてみんながショーを楽しめる状態(=実質的平等)なのです。
裁判所の知恵「合理的区別」
このジレンマに対し、裁判所は「合理的区別」という非常に賢い考え方を示しています。これは、「違いのあるものを、その違いに応じて異なるように扱うことは、理にかなった理由がある限り、憲法違反の”差別”にはあたらない」というものです。
- 駅の点字ブロックやスロープ
- 所得に応じた累進課税制度
- 女性管理職を増やすポジティブ・アクション
- 「女性だから」という理由での不採用
- 特定の国籍を理由とした入居拒否
- 婚外子の相続分を不当に低くすること
結論:私たちが目指す「本当の平等」
本当の平等とは、一人ひとりの「違い」を認め、尊重し、その上で誰もが尊厳をもって生きられるよう、社会として何ができるかを考える「想像力」そのものです。
今日の学びポイント
- 憲法14条は、不当な差別を禁止する基本原則。
- 形式的平等だけでは、かえって不平等を招くことがある。
- 実質的平等を目指すための「合理的区別」が重要。

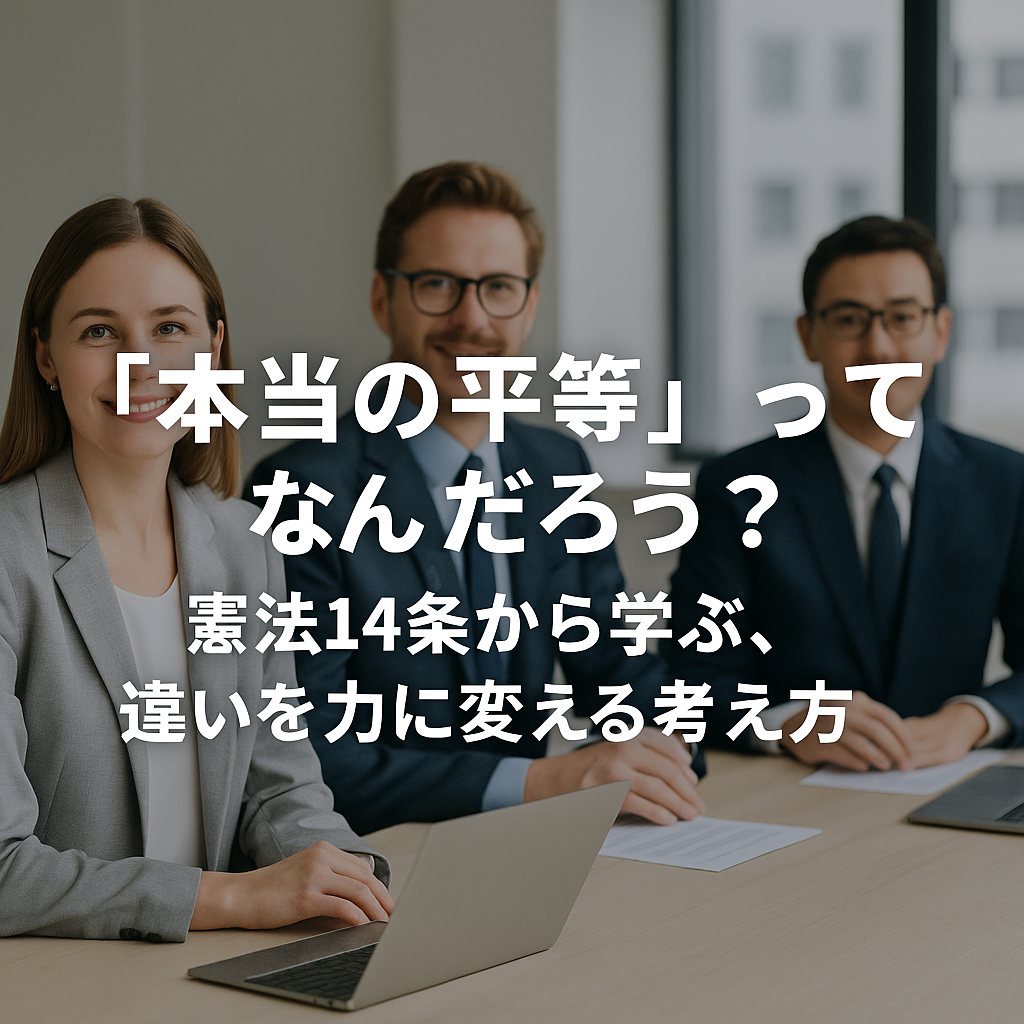
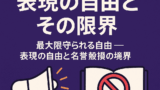
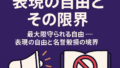
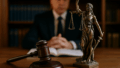
コメント